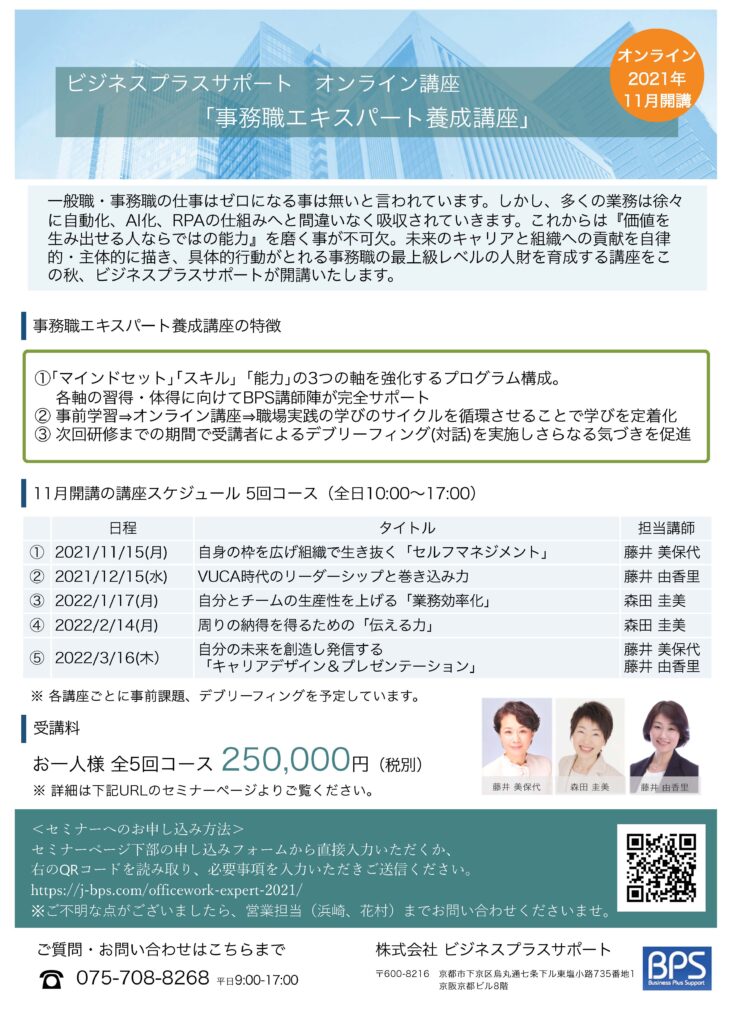東京から金沢に向かう北陸新幹線の中です!
久しぶりの金沢、楽しみですー。
さて、5年前の今日はミャンマーに視察旅行だったと
Facebookが教えてくれました。
ヤンゴン外国語大学の学生さんたちと交流ののちは、ミャンマーワーカー
マネジメントサービスへ。日本に働きに来る予定の若者たちが、キラキラした
眼で懸命に日本語を学ぶ姿を見て、学ぶことの原点を思い起こしました。
まっすぐな笑顔にも心を鷲掴みされました。
この時の視察がきっかけで、一般社団法人ミャンマー人財開発機構を設立。
毎年ミャンマーを訪れていましたが、コロナと内乱で2年間訪れることができて
いません・・。この先数年は、めどが立たないかもです。
そこで、この度社団名を「Freely Life Create」に変えました。
「学ぶことで自由を手に入れることができる。自分の人生を自身で主体的
に創り上げることができる」。そんな想いを込めて、です。
ミャンマー支援はもちろんのこと、国内外問わず、「個人の学び支援」に、
力を入れていきます!