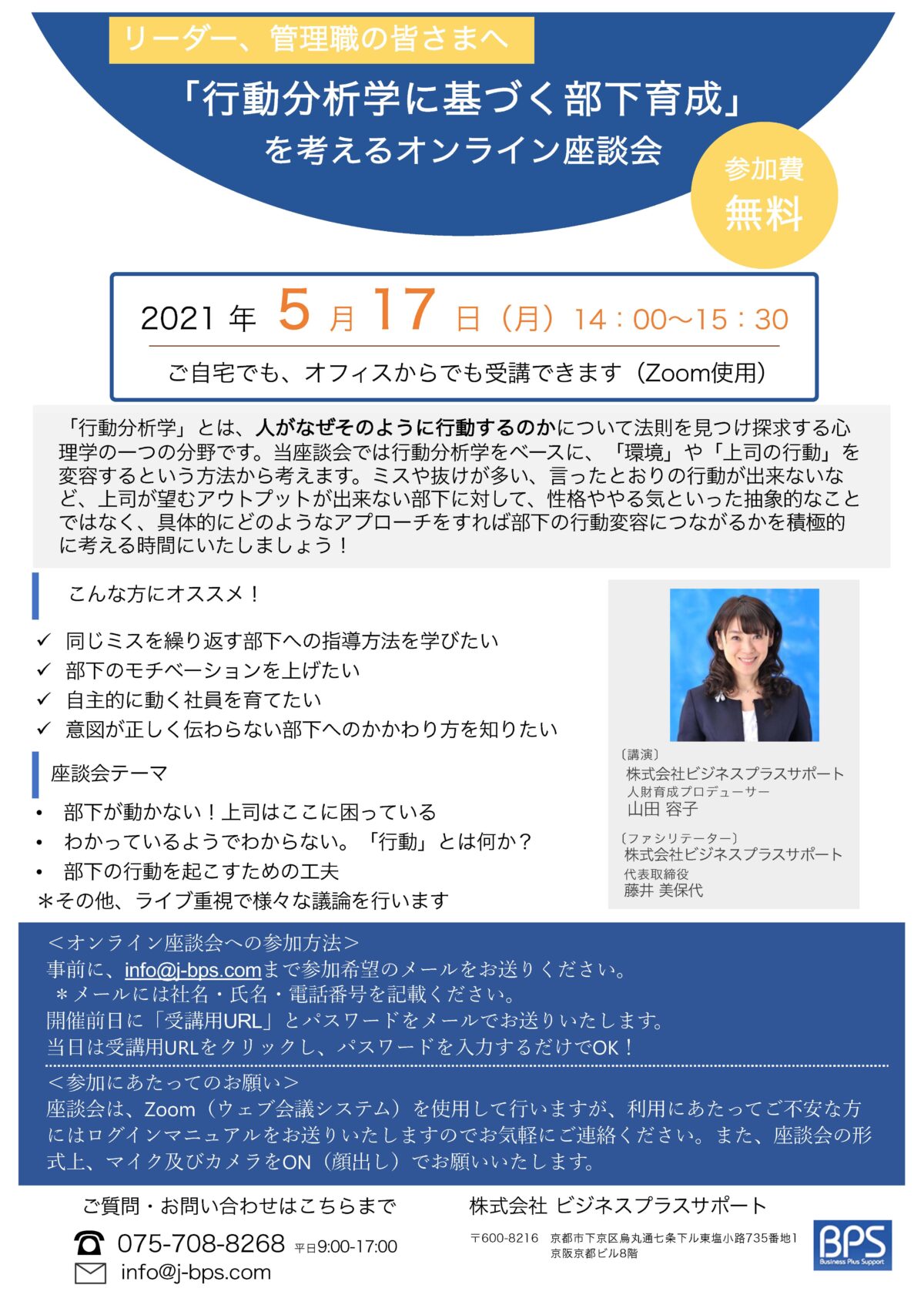週明けの朝は早い!ようやく仕事もひと段落ついたものの、
テクノロジーの課題は積み残す・・。
さて、週末は、clubhouseの「深層対話力で切り取る!日々の徒然」roomでの
対話や、3時間のZOOMでの談合(対話)にと、質濃い時間でした。
深層対話について、田坂広志氏の「仕事の技法」から、ポイントを整理して
おきます。
「仕事の技法」の「根幹的技法」とは何か?それは対話の技法。
なぜなら、どの分野のどの職種のどの仕事であっても、その仕事の根幹は、
商談、交渉、発表、説明、会議、会合、報告、連絡、相談など、すべて、
顧客や業者、上司や部下を始めとする「人間」を相手とした「対話」
だからである。
ここで言う「対話」とは、相手から「メッセージを受け取り」、
相手に「メッセージを伝える」すべての行為のこと。
対話の中でも深層対話の技法を身につけるためには、
日々のすべての「仕事」における言葉以外のメッセージの交換を振り返り、
細やかに、そして深く「反省」することだ。
反省とは、「経験したことを、冷静に、理性的に、省みること」であり、
感情的な側面の強い「懺悔」や「後悔」などとは異なり、
「経験」から「智恵」を掴むための極めて合理的・科学的な方法である。
反省を習慣として身につけることができたならば、深層対話力を高めて
いくことができる。
この時間がとても重要!