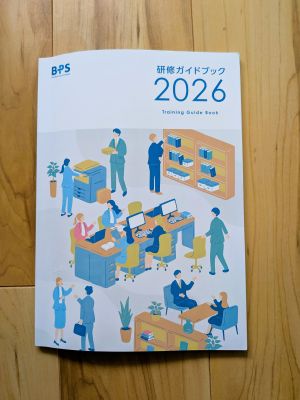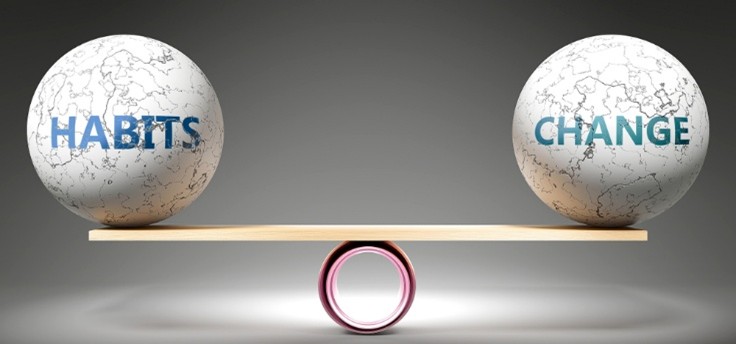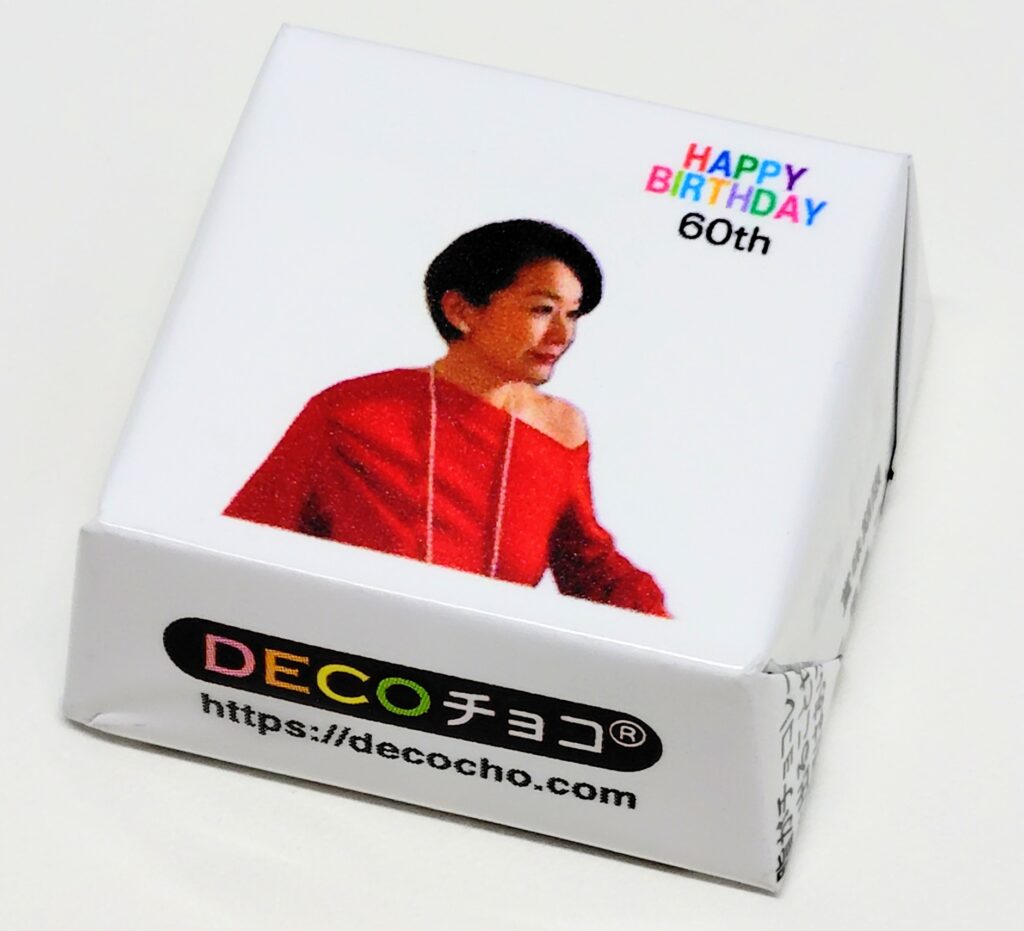皆さんこんにちは、ビジネスプラスサポートの川勝です。
今回は「育休復帰者研修」についてお伝えします。
BPSでは、社内研修のご依頼として、育児休暇からの復帰者、
またその上司の方を対象とした研修をご依頼いただくことがございます。
育児休業からの復帰にあたって不安を抱えていらっしゃる方はまだまだ多く、職場での支援体制や研修の在り方が重要な課題となっているのです。
■育休復帰者研修の必要性
育児休業を経て職場に戻ってくる社員は、「久しぶりの仕事」「新しい環境」「子育てと両立できるだろうか?」といった不安を抱えていることが多いです。
その不安を少しでも和らげるために、企業が研修や面談でサポートすることが大切です。
例えば、育休中に変わった社内制度の説明や、仕事の進め方のアップデート、あるいは「働き方の整理整頓」のような時間管理のコツを学ぶ機会を設けることで、復帰後の不安を和らげ、スムーズなスタートを切ることができます。
■研修は計画的に時期を見て実施すべき
研修のタイミングはとても大切です。
復帰してすぐって、子どもも職場も新しいことだらけの中で研修を詰め込むのは、あまり現実的ではありません。
おすすめなのは、復帰の少し前に「プレ研修」として気軽に参加できる場をつくる、あるいは、復帰後しばらくして落ち着いた頃に改めて実施する。
どちらにせよ、参加しやすい時期を見極めることがカギとなります。
■ 参加者は育休復帰の当事者だけではない
育休からの復帰は本人だけの問題ではありません。家庭ではパートナーと、職場では上司や同僚と、周囲の人の協力があってこそ成り立ちます。
だからこそ、研修の場に上司やパートナーに参加してもらうのが理想的です。
お互いの状況を共有して「こうすればうまくやれるかもしれない」をともに考える機会になれば、職場にも家庭にもいい空気が生まれます。
また、周囲の同じ状況の家庭のやり方を知ることも、多面的な解決策検討に役立ちます。
■ 経験豊富な講師が柔軟な提案をいたします
弊社の講師は、ただ制度に基づいた講義をするばかりではなく、実際に育休から復帰した経験を取り入れた内容をご提案します。
状況をきちんとヒアリングし、「ではこのようなスタイルで実施してみませんか?」と柔軟にプログラムを調整いたします。
育休復帰に向け、他社の人間と話すことも、とても意味のある時間になります。
育休復帰者研修は、社員の不安を和らげるだけでなく、会社全体の風土を少しずつ変えていく大切なきっかけになります。復帰する人だけでなく、まわりの人たちにも「おかえり」と言える職場を目指して、ぜひ前向きに取り組んでみていただきたいと考えております。
もし、「わが社でもやってみたい」「まずは話を聞いてみたい」と感じていただけたら、ぜひお気軽にご相談ください。私たちが、実際の課題に合わせたプログラム内容をご提案いたします。