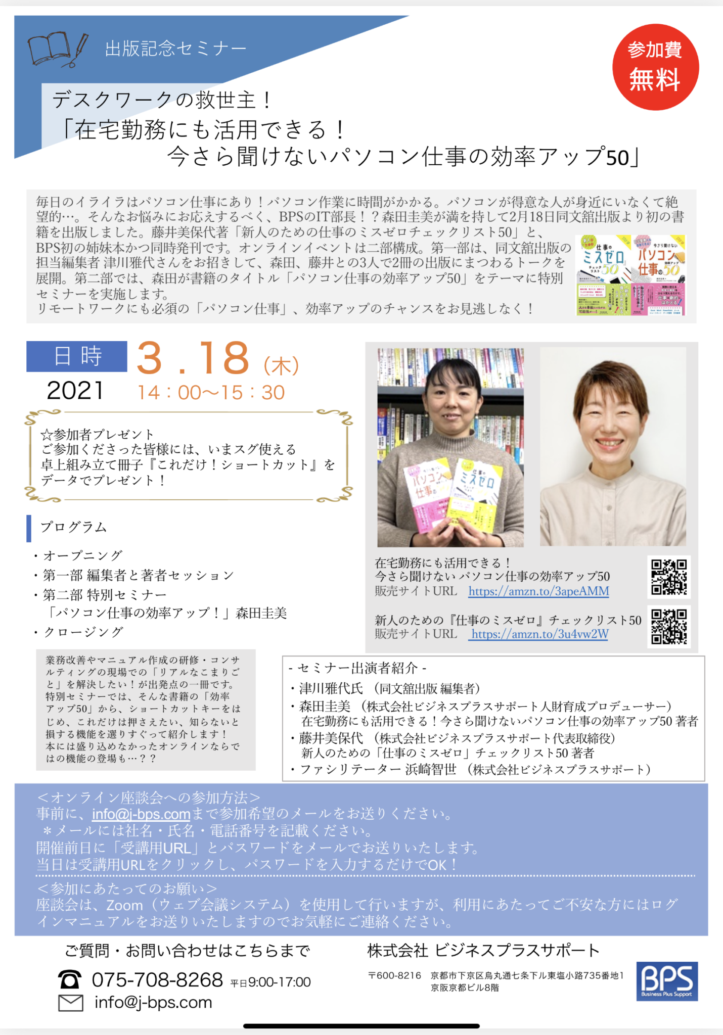渡辺和子氏の「置かれた場所で咲きなさい」は、
バイブル本の一つですが、
今朝もつい手を止め、本の世界に浸る。
何度も繰り返し読んだページ。
以下、本より一部引用します。
『初めての土地、思いがけない役職、
未経験の事柄の連続、それは私が当初考えていた修道生活とは、
あまりにもかけはなれていて、私はいつの間にか
“くれない族”になっていました。
「あいさつしてくれない」。
こんなに苦労しているのに「ねぎらってくれない」。
自信を喪失し、修道院を出ようかとまで思いつめた私に、
一人の宣教師が一つの短い英語の詩を渡してくれました。
その詩の冒頭の一行、それが「置かれたところで咲きなさい」、
という言葉だったのです。
岡山という土地に置かれ、
学長という風当たりの強い立場に置かれ、
四苦八苦している私を見るに見かねて、くださったのでしょう。
私は変わりました。
そうだ。置かれた場に不平不満を持ち、
他人の出方で幸せになったり不幸せになったりしては、
私は環境の奴隷でしかない。
人間と生まれたからには、どんなところに置かれても、
そこで環境の主人となり自分の花を咲かせよう、
と決心することができました。
それは「私が変わる」ことによってのみ可能でした。
いただいた詩は、「置かれたところで咲きなさい」の
後に続けて、こう書かれていました。
「咲くということは、仕方ないと諦めることではありません。
それは自分が笑顔で幸せに生き、
周囲の人々も幸せにすることによって、
神が、あなたをここにお植えになったのは
間違いでなかったと、証明することなのです」
結婚しても、就職しても、子育てをしても、
「こんなはずじゃなかった」と思うことが、次から次に出てきます。
そんな時にも、その状況の中で「咲く」努力をしてほしいのです。
どうしても咲けない時もあります。
雨風が強い時、日照り続きで咲けない日、
そんな時には無理に咲かなくてもいい。
その代わりに、根を下へ下へと降ろして、根を張るのです。
次に咲く花がより大きく、美しいものとなるために』。
「無理に咲かなくとも、根を下へ下へと降ろして、根を張る」。
この言葉が特に響きます!