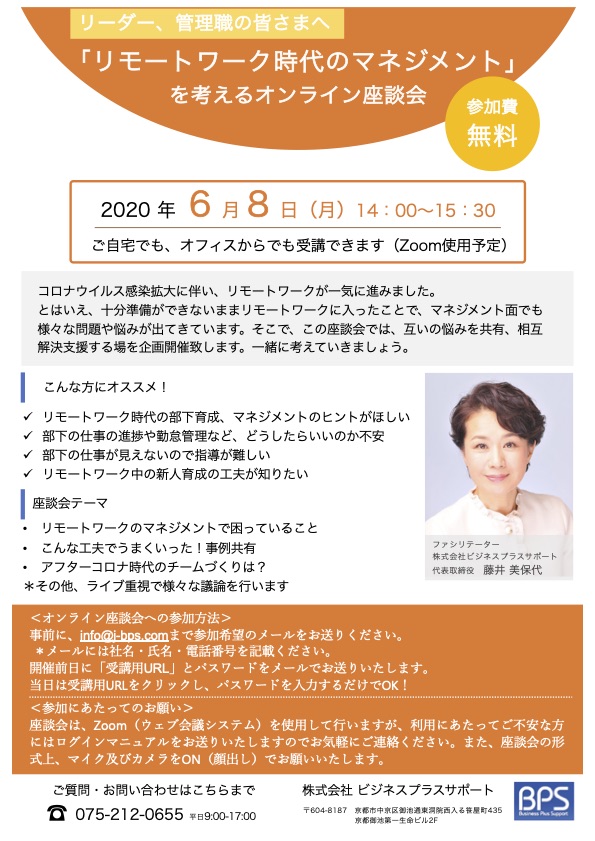最近のお楽しみはNHKオンデマンド。
4年ほど前に放映された番組ですが、
「世界が注目、最新のストレス対策」は面白かった!
日々のストレスはいったいどのようにして
心をむしばみ、うつ病を発症するのか。
そのメカニズムが解説されていました。
ストレスを感じると、ストレスホルモンが
副腎から分泌され、ストレス反応を
体に引き起こします。
その中でも注目されているのがコルチゾール。
これが一定量をこえて分泌されると、
脳の機能を破壊することがわかってきました。
ストレスにさらされ続けると、脳のある部分に変化が
現われます。それは、海馬。
海馬は、記憶をつかさどり、感情にも関わる部分です。
その海馬を構成する神経細胞の突起がむしばまれ、減少します。
もちろん、ストレスを受けたとき身体が反応し、
ストレスホルモンが出るのは、自然の現象。
それは太古の時代、自然の中で生き残るためにも必要なことでした。
生命の危険を感じたときに心拍数が上がり、
緊急事態に速やかに反応できる。
しかし、現代は、人間関係や過多な仕事、睡眠不足など、
絶え間ないストレスにより、ストレスホルモンが出続けている
状態であり、これは危険。コルチゾールを分泌させ続け、
脳を破壊するのです。
そして、その状態を加速するのは、「マインドワンダリング」。
過去のストレスを感じた出来事や、ありもしない未来の不安に
想いを巡らせ続けてしまうことです。
このマインドワンダリングが、私たちの生活の
非常に多くを占めているといいます。
ハーバード大学の行動心理調査によると、なんと
47%に上るとのこと。
つまり私たちは生活している半分近くでストレスを
感じやすい状態になっているのですね。
こうならないためにも、ストレスがかかった時用のコーピング(気晴らし)を
リストアップしておくと、効果的だといいます。
ストレスを感じたときには本を読む、音楽を聴く、
などなるべく数多くコーピングすることが大切。
自らのストレスへの対策を徹底的に繰り返すこと、ですね。
こんな時期だからこそ、”脱マインドワンダリング法”、
リストアップしてみまーす!